知識の暗記に走らず100点!センター化学の賢い勉強法
2017年01月18日 | センター試験

センター化学は、大学受験化学の第一歩だ。 受験生が最初に受験するのはセンター試験であり、その成績は大学の合否をも左右する。
一方で、センター化学は対策をしにくい科目でもある。 暗記事項ばかりかと思ったら計算問題も重要。 出題範囲も広く、何から手をつけたら良いか分からなくなりがちだ。
今回は、センター試験の出題形式・内容とそれに合わせた勉強法について説明する。
何をどう勉強したらよいのか分かりにくいセンター化学。 これを読めば、勉強の道筋が必ず見えてくる。
センター化学の基礎知識
 勉強法の話を始める前に、そもそもセンター化学がどういう科目なのかを理解しておこう。
勉強法の話を始める前に、そもそもセンター化学がどういう科目なのかを理解しておこう。
試験範囲は何か。問題数はどれほどか。 それを知っておいた方が勉強の方針を立てやすいに決まっている。
センター理科、新課程の構成
センター試験の理科は、2015年よりいわゆる新課程に移行した。 科目の構成が大きく変更されたのである。
化学を例にすると、以前は「化学I」「化学II」(各々3単位)という科目区分になっていた。
それが新課程では、「化学基礎」「化学」に変わったのである。 後に詳しく述べるが、内容的には化学基礎が概ね化学I、化学が化学IIに対応している。 大きな違いがもう一つある。 それは、出題範囲が広くなったことだ。
以前のセンター試験では「化学I」のみが試験範囲だったのである。 ところが新課程では「化学基礎」のみならず「化学」からも出題されるようになった。
つまり、高校化学の全範囲が対象になったのである。 理系の受験生はどのみち全て学習するが、それにしてもこの変化は大きい。
当然、内容も高度で難しいものとなる。 受験生としては、センター試験は前哨戦ではなく本番そのものになったのである。
センター化学の出題範囲
次に、センター化学の具体的な出題範囲を知っておこう。 化学基礎、化学別々に見ていく。
化学基礎の範囲
化学基礎は、概ね「化学I」を前身とする科目だ。 高校の授業では2単位として扱われている。 学習内容は以下の通りである。
1. 化学と人間生活 ア 化学と人間生活のかかわり イ 物質の探究 (単体・化合物・混合物) ウ 探求活動 2. 物質の構成 ア 物質の構成粒子 (原子の構造、周期表) イ 物質と化学結合 (イオン結合、金属結合、共有結合) ウ 探求活動 3. 物質の変化 ア 物質量と化学反応式 イ 化学反応 (酸・塩基、酸化・還元) ウ 探求活動赤本ウェブサイトより
「化学と人間生活」は、これから化学を学ぶにあたっての導入と捉えて差し支えない。
単体、化合物、混合物といった基本的な用語がいくつか登場するのみで、そのほかは学習に苦しむ分野ではない。
「物質の構成」は、化学基礎で最も重要な内容である。
原子の構成を学び、電子配置から物質の性質を説明しているためである。
化学反応の理解のうえで欠かせないのが電子の挙動だ。
各物質・原子が持つ反応性は、電子に着目することで理解できる。
また、イオン結合・金属結合といった基本的な結合も学ぶため、のちの内容を理解する上で欠かせない。
「物質の変化」では、化学反応の基礎を習う。
そもそも化学反応はどう表記すれば良いのか。
物質の量はどう定義するか。
化学反応の理解に必要なそうした内容に触れる。
また、酸・塩基や酸化・還元もこの章に含まれる。
酸・塩基の定義は何か、酸化還元反応とはどういうものか。
これを理解しないと、無機化学・有機化学は手に負えない。
このように、化学基礎はそれ自体がハードな内容というわけではないが、のちの学習上大変重要な項目ばかりである。
化学基礎と化学は名目上別の科目だが、内容の面では深い繋がりを持つ。
化学基礎を土台として、そのうえに化学が展開されるイメージだ。
「基礎」と付いているからといって疎かにせずに、全て理解しきるつもりで学習しよう。

化学の範囲
次は「化学」の範囲である。
高校化学のうち、化学基礎に含まれていないもの全てが対象となるため、学習量も当然多くなる。
1. 物質の状態と平衡
ア 物質の状態とその変化 (状態変化、気体の性質、固体の構造) イ 溶液と平衡 (溶解平衡、溶液とその性質) ウ 探究活動
2. 物質の変化と平衡
ア 化学反応とエネルギー (化学反応と熱・光、電気分解、電池) イ 化学反応と化学平衡 (反応速度、化学平衡とその移動) ウ 探究活動
3. 無機物質の性質と利用
ア 無機物質 (典型元素、遷移元素) イ 無機物質と人間生活 ウ 探究活動
4. 有機化合物の性質と利用
ア 有機化合物 (炭化水素、官能基、芳香族) イ 有機化合物と人間生活 ウ 探究活動
5. 高分子化合物の生活と利用
ア 高分子化合物 (合成高分子化合物、天然高分子化合物) イ 高分子化合物と人間生活 ウ 探究活動
赤本ウェブサイトより
高校化学は理論化学・無機化学・有機化学の3つに大別できるが、理論化学のうち化学基礎で扱えなかった残りと無機・有機の全てが範囲に含まれている。
言うまでもなく内容は広大で、短期間でマスターできるようなものではない。
第2章までが理論化学の残りである。
状態平衡、化学平衡といった概念や電池・電気分解の原理を学ぶこととなる。
内容的な難しさもさることながら、平衡定数のような数学的に複雑なものも登場する。
ただ、どれも無機・有機を学ぶ上で大切な足がかりになる。
電池や電気分解の節は、元素のイオン化傾向や酸化・還元といった、化学基礎から勉強してきたことの一つの集大成である。
また気液平衡や蒸気圧の話題は、物質の三態に関する正しい理解が要求される。
すでに化学基礎の内容が前提となっているのだ。
無機分野は、典型元素や金属元素の性質、それに人間生活への応用を学習する。
典型元素といっても窒素や硫化水素のように気体のものもあれば、鉄や銅といった金属もあり様々だ。
通常、「窒素」や「硫黄」のように元素ごとに分類して学習するが、元素ごとといっても単体のみを扱うわけではない。
二酸化窒素やアンモニア、それに硝酸…というふうに、多数の化合物について勉強する。
金属元素では、たとえば錯イオンの色という大きな壁がある。
鉄であれば、鉄(II)イオンと鉄(III)イオンでは色が異なるし、各々様々な錯イオンを形成する。
代表的なイオンについては、その色を正確に覚えなければならないのだ。
このように、知識量が非常に多く、その暗記・整理に苦労するのが無機化学の特徴だ。
有機分野では、様々な有機化合物を扱う。
アルカン、アルケンといった単純な物質に始まり、アルコールやアルデヒド、カルボン酸と官能基の違いで色々な化合物がある。
また、ベンゼンを代表とする芳香族化合物も、種類・反応ともに複雑だ。
無機化学同様、知識面での苦労が目立つ分野である。
一方で、構造決定問題のように思考力も要求される。
分野ごとの配点と問題数
試験範囲を確認したところで、分野別の配点を見てみよう。
化学基礎が新設された2015年以降の設問分析は以下のようになっている。
これまでの配点データを見ると、分野別の配点は概ね
- 理論化学:50点
- 無機化学:25点
- 有機化学:25点
であることがわかる。 理論化学の配点が全体のおよそ半分を占めているのが特徴だ。
一方でどの分野からもそれなりに出題されているのも事実。 化学に限った話ではないが、センター試験では対象範囲全てからバランス良く出題されるものである。 したがって、たとえば有機化学が超苦手だから他の分野で補おう、という考えは失敗に終わる。
上の配点から考えると、有機化学を捨ててしまうと実質75点満点である。 初めから天井を低くしているようなものだ。
大前提として、どの分野も余すことなく勉強するよう心がけよう。 試験時間は60分で100点満点、マーク数は35である。
試験時間に比してマーク数が多いため、素早く問題を解くことが要求される。 勉強の際は、正確性のみならずスピードも意識しよう。
出題される問題と勉強法:理論化学
 センター化学の試験範囲や形式について説明してきた。 次はいよいよ、具体的な問題を見て対策法を説明する。 実際にセンター試験本番で出題された問題を例に考えて行こう。
センター化学の試験範囲や形式について説明してきた。 次はいよいよ、具体的な問題を見て対策法を説明する。 実際にセンター試験本番で出題された問題を例に考えて行こう。
理論化学の知識問題
問題冊子を開いてまず目に入るのが、理論化学の知識問題。 具体的な次のようなものである。
第1問 問1 次の(a,b)に当てはまるものを、それぞれの解答群の1~5のうちから一つずつ選べ。 a 固体が分子結晶のもの 1 黒鉛 2 ケイ素 3 ミョウバン 4 ヨウ素 5 白金 b 分子が非共有電子対を4組もつもの 1 塩化水素 2 アンモニア 3 二酸化炭素 4 窒素 5 メタン2017年センター化学問題より
最初に必ずこのような知識問題が用意されている。
もちろん、完全な丸覚えをせずとも解けるだろうが、答えに至るには物質や元素の性質についての知識が不可欠だ。
ここでしっかり得点しておかないと、いきなり出鼻をくじかれて周囲に差をつけられてしまう。
難関校受験生であればなおさら、余裕で正解しておきたいところだ。
勉強法としては、教科書を読むのが第一である。
物質の性質の大抵は、元素の電子配置や極性によって説明できる。
たとえばヨウ素の場合、ヨウ素は17族の元素であるから、共有結合(単結合)をすれば安定になる、というふうに自分で理屈を立てて説明できるようになれば、こうした知識問題も正解できるようになる。
なんでもかんでも暗記するというのは賢い方法ではない。
最低限の原理や性質は暗記するが、それから先は自分の力で考えることで正解を導き出せることを忘れずに。
理論化学の計算問題
理論化学の計算問題には、熱化学方程式、化学平衡、電離度など様々な分野が該当する。
たとえば次のような出題例をみよう。
第2問
問3
ある濃度の過酸化水素水100 mLに、触媒としてある濃度の塩化鉄(III)水溶液を加え200 mLとした。
発生した酸素の物質量を、時間を追って測定したところ、反応初期と反応全体では、それぞれ、図1と図2のようになり、過酸化水素は完全に分解した。
この結果に関する問い(a,b)に答えよ。
ただし、混合水溶液の温度と体積は一定に保たれており、発生した酸素は水に解けないものとする。
a 混合する前の過酸化水素水ん濃度は何mol/Lか。最も適当な数値を次の1~5のうちから一つ選べ。(選択肢略)
b 最初の20秒間において、金剛水溶液中の過酸化水素の平均の分解速度は何mol/(L・s)か。最も適当な数値を、次の1~5のうちから一つ選べ。(選択肢略)
これは知っている知識を答えるものではなく、その場で与えられたデータをもとに計算するものである。
ただ内容を暗記していれば良い、という訳ではない。
とはいえ、このレベルの計算問題は学校教科書やその傍用問題集に載っている。
それらを用いて少し問題演習しておけば十分解けるものだ。
よって、そこまで警戒することはないし、ましてや難しい問題集を買って取り組む必要はない。
学校で配られるような教材を丁寧に学習しておけばそれでOKだ。
理論化学では、細かい知識の暗記に走るのではなく、少数の基礎原理から様々な現象を説明するのがカギである。
その勉強法を以下の記事で詳説しているので、方針に迷ったらこれを読んでほしい。
出題される問題と勉強法:無機化学
 次に無機化学の問題を見てみよう。 理論化学とは逆で、無機では知識問題が中心となる。
次に無機化学の問題を見てみよう。 理論化学とは逆で、無機では知識問題が中心となる。
無機化学の知識問題
無機化学の知識問題として代表的なのは、やはり「イオンの色」や「金属イオン分析」である。 たとえば次のようなものだ。
Al3+、Ba2+、Fe3+、Zn2+を含む水溶液から、図3の実験により各イオンをそれぞれ分離することができた。この実験に関する記述として誤りを含むものを、下の1~5のうちから1つずつ選べ。
- 操作aでは、アンモニア水を過剰に加える必要があった。
- 操作bでは、水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える必要があった。
- 操作cでは、硫化水素を通じる前にろ液を酸性にする必要があった。
- 沈殿アを塩酸に溶かしてK4[Fe(CN)6]水溶液を加えると、濃青色沈殿が生じる。
- ろ液イに塩酸を少しずつ加えていくと生じる沈殿は、両性水酸化物である。
- 沈殿ウは、白色である。
イオンの分析では様々な種類の反応が起きる。
上の問題でも、操作a~cのそれぞれが具体的にどういう反応なのか理解していないと、問題を解くことができない。
どれか1つでも抜けがあったら、正解率は急落してしまうのだ。
無機化学の知識問題は、「関連する反応を全て知っていないと答えを出せない」のが大きな特徴だ。
知識に穴があるとどうしても正解できない。
したがって、時間をかけてでも正確性を追求して勉強する、というのが無機化学の急所である。
理論化学や有機化学では大まかな性質・原理を知っていればなんとかなる問題が多い。
しかし無機化学ではそれが通用しないのだ。
正確な知識を得るためには、やはり反復学習が欠かせない。
1回の学習で全て覚えるのは当然不可能であるから、何度も教科書や参考書を読んで塗り固めていくことが必要だ。
無機化学の学習で一つ効果的な方法は、資料集を駆使することである。
イオンの色や沈殿の有無は、たとえば「濃青色沈殿」のように文章で説明されるよりも実際に写真を見た方が覚えやすいに決まっている。
受験勉強で資料集を役立てている生徒は少ない。
だが、上手に活用できれば大きな成果を生むのだ。
勉強の流れとしては、まず教科書を読み、必要に応じて資料集を参照する、というのを繰り返す。
空いた時間や電車内でのスキマ時間を活用して、継続的に学習しよう。
何度も読んでいくうちに知識が定着してくる。
そうしたら初めて問題集に着手するのだ。
いきなり問題集に着手するのは愚策である。
わからない問題が多すぎて、モチベーションを削がれるだけだからだ。
計算問題
無機化学は知識問題が花形なのは確かだが、計算問題もいくつか登場する。
内容は酸化還元反応がメインだ。
第3問
問4
銅と亜鉛の合金である黄銅20.0 gを酸化力のある酸で完全に溶かし、水溶液にした。
この溶液が十分な酸性であることを確認した後、過剰の硫化水素を通じたところ、純粋な化合物の沈殿19.2 gが得られた。
この黄銅中の銅の含有率(質量パーセント)は何%か。最も適当な数値を、次の1~8のうちから一つ選べ。(選択肢略)
化学をある程度勉強している人ならわかることだが、この問題は無機化学が舞台となっているだけで、中身は反応式の量的関係である。
理論化学で学ぶような、係数と物質量の関係を知っていれば、少しの計算により答えを導き出すことが可能だ。
こうした問題も、教科書の練習問題レベルを丁寧に解いていればすぐに解けるようになる。
その代わり、計算の正確性を追求するべきである。
センター試験はマーク式なので、計算ミスで他の答えを選んでしまうと0点だ。
記述式と違い、そこに加点の余地はない。
日頃の問題演習でも、計算ミスはゼロにするつもりで問題を解いてほしい。
無機化学の詳細な勉強法については、次の記事でも説明している。
知識は完璧にし、かつ暗記に偏らない。
それを実現する方法を述べているので、受験生必見だ。
出題される問題と勉強法:有機化学
 理論、無機と来て次は有機化学だ。 有機化学は知識と計算どちらもバランス良く勉強する必要がある。
理論、無機と来て次は有機化学だ。 有機化学は知識と計算どちらもバランス良く勉強する必要がある。
有機化学の知識問題
有機化学の知識問題の例を見てみよう。
第4問 問1 エチレン(エテン)とアセチレンに共通する記述として誤っているものを、次の1~5のうちから一つ選べ。
- 水が付加するとエタノールが生成する。
- 重合して高分子化合物を生成する。
- 触媒とともに十分な量の水素と反応させるとエタンが生成する。
- すべての原子が同じ平面上にある。
- 水上置換で捕集できる。
有機の知識問題には一つの特徴がある。
それは、知識を丸暗記していなくてもその場で考えて答えを出せることだ。
上の問題で、1~5の知識の真偽を完全に暗記するのは無理がある。
そこで、基礎的な知識だけを基にこれを解いてみよう。
二重結合や三重結合を持つ物質が重合するのは自然な話だ。
実際、ポリエチレンやポリアセチレンは存在するので、2は正しい。
次に3だが、これは当然正しい。
水素を与えているのだから、二重結合が解かれて水素と結合する。
二重結合や三重結合は回転することができない。
このことから4も正しいと推測できる。
また、エチレンやアセチレンは炭素・水素原子のみで構成されており、大きな極性を持たない。
したがって水には溶けにくく、水上置換で捕集できる(5)。
以上より正解は1だ。
エチレンの方は無問題だが、アセチレンに水を付加してもエタノールにはならない。
そもそも原子の数も合わないし、二重結合に-OH基がついている化合物は不安定なのであった。
このように、有機化学の、特に化合物の性質に関する問題はその場で考えて解けるものが多い。
原子の電気陰性度や官能基の性質といった基礎知識さえ身につけておけばあとは怖くない。
教科書をよく読んで、これらの内容を早いうちに覚えてしまうことをオススメする。
そうすれば、問題集などの解説を読んだ時に「なるほど!確かにそうだ。」とすぐ納得できるようになる。
勉強が圧倒的にスムーズになるに違いない。
有機化学の計算問題
有機化学は計算問題もよく出題される。
しかし、怯む必要はない。
有機化学における計算問題は、出題内容は限られているのだ。
典型的なのは次のようなものである。
第4問
問4
化合物Aは、ブタンと塩素の混合気体に光をあてて得られた生成物の一つであり、ブタン分子の水素原子1個以上が同数の塩素原子で置換された構造をもつ。
ある量の化合物Aを完全燃焼させたところ、二酸化炭素が352 mg、水が126 mg生成した。
化合物Aは1分子あたり何個の塩素原子を持つか。
正しいものを、次の1~6のうちから選べ。
ただし、化合物Aのすべての炭素と水素は、それぞれ二酸化炭素と水になるものとする。(選択肢略)
有機分野での計算問題は、大抵上のような分子量・構造に関するものばかりである。
分子量を求めて、そこから分子の構造を探る、という形式である。
実は、こうした問題は有機化学の知識がそこまで深くなくても解けるのだ。
実際の試験の場では、計算問題というだけで後回しにしてしまうケースが少なくない。
だが有機の計算問題はこの限りではない。
見た目に圧倒されずに挑戦してみると、案外簡単に答えを得られるものだ。
計算問題のために特別な対策を施す必要はない。
授業や定期試験で登場する問題をサクサク解けるレベルになれば十分だ。
繰り返しになるが、難関大志望者向けの難しい問題集に無理して挑戦することはない。
有機化学は暗記で押し通す分野と勘違いされやすい。
確かに暗記すべき事項も多いが、理屈で答えを導く努力も忘れずに。
知識と思考のバランスを保って勉強する方法を、次の記事で解説している。
有機分野をこれから勉強する人は、忘れずに読んでおこう。
日頃の学習に際して
 最後に、普段の化学の学習で気をつけるべきポイントを説明する。 また、効率的に勉強できる参考書にも触れておこう。
最後に、普段の化学の学習で気をつけるべきポイントを説明する。 また、効率的に勉強できる参考書にも触れておこう。
構造式や反応式を必ず描こう!
教科書を読む時も問題演習の時も、化学では多くの化合物や反応と出会うこととなる。
そして、そのうち多くは大学受験のためには覚えるべきものである。 そこで重要になるのが構造式・反応式をノートに描くということだ。
たとえば「ニトロベンゼン」という文字列を読むよりも、実際の構造式を描いてみた方が、分子の形状やその性質をイメーズしやすい。
他にも、「水を電気分解すると水素と酸素になる」と言われるよりは「2H2O → H2 + O2」という反応式を見た方が、どういう反応が起きているかイメージできるし印象に残りやすい。
こうした理由から、ノートに構造式や反応式を明記した方が学習効果は向上する。
いちいち描くのは初めのうちは面倒に感じるだろうが、解く問題が難しくなればなるほど、この習慣がいかに優秀か実感できる。
初めのうちは我慢して、こまめに構造式・反応式を描いてみよう。 わからない式があれば、教科書を開いて調べれば良い。
知らない情報を本で調べるというのも、受験で役に立つ習慣である。
資料集を活用しよう!
無機化学の分野でも述べたが、化学の学習に資料集は欠かせない。
物質やイオンの色は、文字であれこれ言われるよりも写真で見れば一目瞭然だ。
だが、資料集の良いところはそれだけではない。 たとえば緩衝液の性質とその原理を知りたいとする。
酢酸と酢酸カルシウムの水溶液がなぜ緩衝液として機能するのか。 教科書には、必ずこれの説明が載っている。
しかし、初見の生徒にとっては文章を一読するのみでは理解しきれないものだ。 そういう時に、資料集が活躍する。
緩衝液の項目では、酸を加えた場合、塩基を加えた場合のそれぞれについてなぜpHの変化が小さくなるか、図で明快に説明されている。
細かな情報や文字による説明はもちろん教科書や参考書に軍配があがるが、図による明快な説明では資料集が大きく勝る。
学校で、必ず1冊は資料集をもらっているはずである。 授業の時のみではなく、自学習においても積極的に活用しよう。
化学は暗記科目ではない
化学=暗記科目、と思っている受験生は実は多い。 だが、ここまで読んで来たあなたなら、それが誤った考え方だと理解できるはずだ。
確かに、暗記しなければならない知識は多い。 特に物質の色や命名法などは、そのまま暗記するしかないものである。
だが、センター試験に出題される問題は、自分で考えて解決できるものの方が多いのだ。
最低限の基礎知識・原理から出発して、物質の性質や反応を説明する。 この営みを忘れないようにしよう。
思考力が不十分なうちは、苦労も多い。 だが慣れてくれば、むしろ高校化学で必要な知識が案外少ないということに気づく。
その発見は、あなたの化学学習が軌道に乗ってきた証拠だ。
役立つ問題集
教科書のみの学習では不安だろうから、参考書の紹介もしておこう。 センター化学の参考書選びのコツは、
- 知識の暗記に偏っていない
- 問題が過度に難しくない
- 図表が豊富である
といった点である。 例としてあげるならば、「岡野の化学が初歩からしっかり身につく」がある。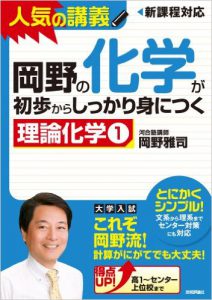 本シリーズ最大の長所は、何と言ってもその簡明さにある。 いきなり難しい内容や細かな知識の解説から始まっても、読者は困惑して取り残されてしまうのみである。
本シリーズ最大の長所は、何と言ってもその簡明さにある。 いきなり難しい内容や細かな知識の解説から始まっても、読者は困惑して取り残されてしまうのみである。
本書は化学を勉強したことのない初学者であっても、問題なく理解できるよう設計されている。
図表も豊富で、退屈しない上に印象に残りやすい。 初めの1冊、何を使えば良いか悩んだらコレを使ってみるのも悪くない。
問題集も、そこまで難しいものではなく、基礎を着実に習得できるシンプルなものが望ましい。
その点優秀なのが「らくらくマスター化学基礎・化学 (河合塾シリーズ)」である。 シンプルな問題が中心であるのが「らくらくマスター」の長所だ。 解説も丁寧であり、それでいて問題数が充実(計300問程度)しているのも見逃せない。
シンプルな問題が中心であるのが「らくらくマスター」の長所だ。 解説も丁寧であり、それでいて問題数が充実(計300問程度)しているのも見逃せない。
これ1冊を仕上げれば、センター化学で困ることはない。
過去問の使い方
センター試験対策として、多くの人は過去問を解く。
現代文のような科目では過去問演習が大きな成果を生むのだが、センター化学ではこの限りではない。 第一に、そもそもセンター理科が新課程になったのは2015年のことで、過去問のストックが少ない。
いまの出題範囲・出題形式と一致している過去問がたった数年しかないのだ。
それ以前の過去問も入手は可能だが、「化学I」は現在の試験範囲よりもかなり狭くなっており、試験対策として機能しないというのが正直なところだ。
第二に、過去問演習で化学の学習をするのは効率が悪い。 知識の暗記をしたいのであれば、教科書や通常の問題集の方が内容にまとまりがあって効率的である。 センター化学の過去問は、あくまで
- 出題形式を知ったり、時間配分を考えたりする
- どの分野が苦手か、弱点を把握する
といった使い方に止めることを推奨する。 問題演習の材料としては、セミナー化学のような学校で配布される問題集でも十分だし、上に紹介したような問題集を購入するのも一つの手段だ。
まとめ
 センター化学の出題形式や内容を紹介した後、過去問を例にして具体的な問題とその勉強法を説明した。
センター化学の出題形式や内容を紹介した後、過去問を例にして具体的な問題とその勉強法を説明した。
暗記事項が多い高校化学。 確かに知識の暗記は必要だが、それ以上に思考力・計算力も欠かせない。
だがこうした力は決して入手困難なものではなく、教科書や傍用問題集などをこなせば自然と身につくのだ。
まずは焦らず教科書の内容理解から始めよう。 その際、資料集を活用することも忘れないように。
ある程度内容が定着してから問題演習をすればよい。 最低限の知識は正確に身につける。 だが、そこから先は自分の頭で考えて問題を解決していく。 順を追った正しい勉強法で、センター化学を突破しよう。
慶早進学塾の無料受験相談
- 勉強しているけれど、なかなか結果がでない
- 勉強したいけれど、何からやればいいか分からない
- 近くに良い塾や予備校がない
- 近くに頼れる先生がいない
そんな悩みを抱えている人はいませんか?
各校舎(大阪校、岐阜校、大垣校)かテレビ電話にて、無料で受験・勉強相談を実施しています。
無料相談では
以下の悩みを解決できます
1.勉強法
何を勉強すればいいかで悩むことがなくなります。
2. 勉強量
勉強へのモチベーションが上がるため、勉強量が増えます。
3.専用のカリキュラム
志望校対策で必要な対策をあなただけのカリキュラムで行うことができます。
もしあなたが勉強の悩みを解決したいなら、ぜひ以下のボタンからお問い合わせください。




